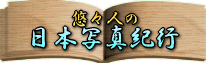
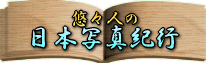
体 温
| 小さい時から、一般の人にとって、もっとも馴染みのある医療機器と言うと、あのガラス棒で出来た水銀式の体温計であろう。M社や、T社などは、体温計メーカーとして、知らない人はいないぐらいである。 そして小さいときの思い出として、お母さんに無理矢理に腋の下に体温計を差し込まれ、上から腕を押さえつけられ、窮屈な思いをしたことがあるであろう。その時の測温時間の長かったことも、不快な思い出として、今でも残っていることと思う。そして、今日は7度5分もあるから、家でおとなしくしていなさいと、無情な宣告をされたことがあると思う。プールの嫌いな子は、熱があるとさぼれる(見学)と喜んだ人もおられるかもわからない。それこそ悲喜こもごもな話題に事欠かないほど、普及した医療機器であった。 これほど、普及した体温計も、元は病院でのみ使われていたのである。血圧計も、最近でこそ家庭でも使われているが、これも、もともとは病院で使われていた機器である。当初は厚生省は頑として家庭用としては認めなかった。ご承知の様に、今では家庭用血圧計が当然の様にして、家電量販店やスーパーの店頭に並んでいる。 さて、話を戻そう。体温計も、昭和40年代に電子化の波が押し寄せ、電子体温計が市販されるようになった。当時の電子体温計は、今と違い文庫本や、タバコサイズで、表示も液晶では無く、針式メーターや蛍光表示管、LEDであった。センサーは今と同じサーミスタであった。当時は、まだLSIやCPU(マイクロプロセッサー)が無く、OPアンプと、ロジック(やっとTTLから、低消費電力のC−MOS ICが出回り、使われるようになった。)で組んだものだ。値段も高く(5〜8万円位)、また、小さくするのには限りがあった。病院向けとして、電子体温計と脈拍計もH社より発売された。当時は、イギリス製で25万円位したのを医科向けとして10万円以下で発売された。これは、赤色のLEDが使用されていた。しかし、共に期待するほどは売れなかった。コストが高かった。 そして、致命的であったのは測温時間が、ガラス式の体温計と変わらなかったのである。サーミスタを使用した温度計の立ち上がりは早く理想的なはずであったが、肝心の体温が上がらないのである。腋下を開いて、センサーを差し込むわけであるが、その時、肝心の腋下の温度は、室温に影響され、下がってしまうのである。それが、回復するまでになんと、7分以上かかるのである。これでは、いくら機械が優秀であってもどうしょうも無かった。そこで、各社が言い出したのは、舌下で測ってくれと言うことであった。そして、衛生上の問題で、センサーにかぶせる透明なポリエチレン製のプルーブが添付された。ちなみに、機械そのものは、恒温水槽で計ると、5、6秒で、正確な温度が測れるのである。 しかし、それでも正確な体温を測ろうとすると、5分以上はかかった。次に開発されたのが、予測式体温計である。これは、腋下でも、舌下でも良かった。センサーを被測定部に入れ、最初の1分間の温度の立ち上がり状況を、統計処理し、10分後の体温を予測して報知させるものであった。一見画期的であった。しかし、ご承知のように、大阪の数学者により、その嘘が暴かれ、メーカーは大量の予測式体温計の回収をせざるを得なくなった。所詮、目安でしかなかった。人によって、当てる場所によって、周囲温度によって、最終到達体温が極端に違ったのである。 病院では、手術中は、直腸温が一般的であった。経時変化をとらえるには、周囲の温度変化に影響されない部位が良かったのである。しかし、それでも異物であるセンサーを挿入すると、体温は変化してしまうのである。従って、経時変化をとらえるのには、良いが早く正確に体温を測ろうとするには、いずれにしろ不可であった。 そこで、登場したのが鼓膜温計であった。医師の間では、鼓膜の温度は深部体温と同じと言われ、わざわざ小さなサーミスターを鼓膜に接触させ、測定していたのである。しかしこれでは、リスクが多いとのことで出現したのが、赤外線式の鼓膜温計であった。例によって、最初のに市販したのは米国であった。当時(10年前)で日本円にして10万円くらいであった。 当然、日本のメーカーが静観しているはずが無く、各社で開発が行われた。その開発競争に勝って市販したのが、ともに上場会社であるO社とH社であった。厚生省は日本では前例が無いとのことで簡単に認可しなかったため、期せずして同時に認可がおり、2社が発売開始となった。その後、M電気とK社が続いてきた。共通しているのは、すべて医家向けで、製薬会社のブランドでの発売となった。製造メーカーにしてみれば、自分で売るには自信が無かった。価格も高かった(6万円〜8万円)うえ、取り扱いが難しかった。 そこで、病院の専門家向けとして、その専門家に強い製薬会社の販売網に頼ったのである。しかし、その結果、どこも失敗した。取り扱いが専門家でも難しかったのである。理由は、簡単で、専門家でさえ、この鼓膜温計のプローブ先端を、鼓膜に向けることが出来なかったのである。鼓膜に向いていないと、鼓膜以外の温度を計測し、低めに表示されてしまうのである。外耳道の温度は、空気に触れている分、実際の温度が低く、それを計ると当然、実際の体温より低めに測定されてしまうのである。 死体の解剖に立ち会ったことがあるが、この外耳道は人によって形状がまちまちで、すんなり鼓膜に鼓膜温計の測温プローブを鼓膜に向けることが出来ないのである。この結果、測定の度に測定値がばらつき、安定した値が得られないのでは、当然実用的では無かった。(但し、幼児の場合は、外部より鼓膜が比較的見えやすいため、有効とのデータも出ている。) そこで、出てきた、最近の鼓膜温計は、「耳温計」と称し、何とあの予測式体温計と同じように、統計的処理をして測定しようというものである。つまり、いつも、測温プローブが鼓膜を指すとは限らないので、諦めて、耳の中の温度を何回か計り、統計処理して表示しているのである。むしろ、鼓膜を計るのを諦めているのである。ちなみに、鼓膜温は腋下温に比べ、平均で0.5度高い(外耳道の温度は、人にもよるが、鼓膜より1度から3度も低い)のであるが、この耳温計は、通常の体温と殆ど変わらない表示をするのである。そして、再現性がすこぶる良いのである。これが、今出回っている耳温計の実体なのである。 知り合いの医師は、患者のお腹を手で触り、熱の有無を見ているので、体温計は不要といっている。確かに、外来ではこれで十分であろう。と言うことは、所詮目安なのである。そう思えば、数秒で計る耳温計は、それで意味があるといえる。 しかし、一つの基準として、きちんと体温を計ると言うことは、結局、水銀式であれ、サーミスタ式であれ、それなりの時間が掛かると言うことなのである。目安として考えるなら、耳温計は不要で、それこそ額と額を付けて判断する方法で十分と言うことになる。これは、古来より用いられてきた方法である。 |
0009
Hitosh
| TOP | 北海道 | 東 北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | 中国四国 | 九州他 |