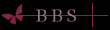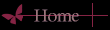竹本偲は目当ての人物を窓際に見つけて微笑んだ。早足で近づいて行くと、偲に気がついて振り向いた。
にっこり笑うと可愛らしさが増す。
同性でも、綺麗なものは綺麗だし、可愛いものは可愛い。
お嬢さま育ちで天然ボケなのに、こう見えてもアイドル歌手の卵だ。友人の欲目を差し引いても、容姿端麗で、歌もそこそこ聴かせる。でも、魑魅魍魎が跋扈する芸能界で生き伸びて行けるのかなと、偲は不安だ。
なまじ、保護者がミュージシャンなんてものをやっているから、余計な話が耳に入ってくるのだ。
「ゴメン、待った?」
美術室の掃除当番を終えて、偲は図書室で待っている友人の元へ急いで来たのだ。
「大丈夫よ。面白いもの見つけちゃったし」
母親の影響で本好きの友人は、そう言って手にした新書を偲の目の前に突きつけた。
「『私説 西遊記 著書、竹本由之』 由之君って、小説も書いてたんだね」
「今じゃ、由之君、ミュージシャンというよりも、タレントだものね」
溜息混じりに偲は保護者について評した。
「でも、今日はミュージシャンなんでしょう。ニューアルバムのレコーディングだっけ?」
「新譜は新譜なんだけど。ソロじゃないみたい」
偲は軽く首を傾げた。
「そう」
大きく頷いて、北原莉奈は満面の笑顔を見せた。
相変わらず黒ずくめのボディガードが中心街に向けて軽やかに車を走らせて行く。
北原家母子二代に渡り、ボディガードを勤めるブラックアイズは北原家の専属である。
元々は莉奈の母の実家がお目付役として遣わしたのだが、今では北原がその全権を掌握しているらしい。偲にとっても、馴染み深いこの黒いスーツの運転手は、そのシャープな外見とは裏腹に別名を北原母子のファンクラブ会長と言われるくらいの、お嬢さま第一主義である。
完璧な運転で目的地に車を横付けさせた黒服の運転手に、莉奈は笑いかけた。
「坂田さん、ご苦労さま。終わったら電話するわ」
「畏まりました」
礼儀正しく一礼して、坂田は車に乗り込んだ。
「莉奈、デビューしても付き人いらないみたいね」
「どうして?」
おっとりとした笑顔で親友は振り向いた。
「ブラックアイズがそんなことさせないんじゃない」
とはいえ、偲にとっては完全に他人事だ。
生まれた頃から姉妹同様の付き合いをさせてもらってはいるものの、北原家は竹本の家とは格が違いすぎる。
レコーディングスタジオの受付で莉奈が名前を言うと、スタジオのナンバーを教えてくれた。
保護者がミュージシャンの偲よりも莉奈が馴れているのはちゃんとした理由がある。
アイドル歌手の卵として頻繁に出入りする以前に、しょっちゅう入り浸っていたせいだ。簡単な話、莉奈の母親である優子にやたらと音楽業界の知り合いが多く、そのほとんどが莉奈をレコーディングスタジオで遊ばせた経験があるのだ。
105と書かれた古いスタジオのドアを開けると、竹本由之の甘い声が耳に飛び込んできた。どうやら先にリハーサルを始めていたらしい。
「やあ、待ってたよ」
竹本由之、三十二歳。偲の保護者であることは間違いないが、無論、実の父親ではない。戸籍上は叔父である。
スタジオの中には由之と同年代と思われる男が四名と、明らかに業界人とわかるスタッフが数名、そしてこれまた明らかに場違いな男が一人いた。
莉奈はその場違いな男を真っ直ぐに見つめると、にこやかな笑みを零した。
「えっ、莉奈。あの人知ってるの?」
偲が訝しく思うのも無理はない。偲にとっては全く初めて見る顔だ。
「知らないわ。一度公園で見かけたことがあるだけ」
それにしちゃ、えらく親しげな笑顔じゃないか。
偲の思いをよそに、莉奈はその謎の男に近づいて行った。
一度しか見たことのない美少女がにこやかな笑みを浮かべて近寄ってきて、動揺しない男はまずいない。西野匠も同じだった。
「北原莉奈です。ちゃんと話するの、初めてですね」
「西野匠という」
ぶっきらぼうとも言える返事にもめげず、北原の御令嬢は、嬉しそうに笑った。
どうやら、莉奈の知り合いだと気づいたメンバーが、ほっとした顔で二人を見つめた。
「こっちは構わないよ。どうせこの状態じゃ、仕事にならない。僕らは休憩してるから、だろうリーダー」
ヘッドホンを外しながら、竹本由之は答えた。リーダーと呼ばれた小太りの男も同じように頷き返した。
いろんな人間が出入りするスタジオではあるが、全くの初対面の男を、少しは気にしていたらしい。
「そこらへんの椅子、適当に使っていいよ。話が終わったら呼んで下さい」
どう見ても日本人には見えない大柄のハンサムガイが流暢な日本語を投げる。
「ありがとう、クリス」
莉奈が振り向いて手を振った。
パイプ椅子に落ち着くと、匠はようやく重い口を開いた。
「名前は西野匠。二十五歳。仕事は葬儀屋をしている。ここには、仕事で来た」
「仕事って言っても、まさか死体がここにあるわけじゃないでしょう」
さすがに気味が悪くなったのか、莉奈は辺りを見回した。
「裏家業だ。死体になっても、この世に未練のある連中の始末が俺の仕事でね。でも、あんたがいるんなら、それもなくなるな」
「どうして莉奈がいると仕事にならないの」
莉奈にくっついてこの場に残っていた偲が訊いた。
「あんたは?」
「莉奈の友達で、さっき出ていった、竹本由之の姪」
匠は合点したように頷いた。
中山が見つけてきたアイドルオタクの腕はたいしたものらしい。莉奈のみではなく、竹本偲もきちんと隠し撮りしている。
だが匠が口にしたのはある意味もっと、とんでもないことだった。
「彼女が歌うと、どういうわけか、霊が浄化するんだ」
聞き馴れない答えに、二人の少女は顔を見合わせた。
当惑した女子中学生相手に、匠は言葉少なく、公園での出来事を話した。
「それって、偶然じゃないの。確かにこの子は昔から所構わず歌を癖はあるけど、そんな話、今まで聞いたことない」
莉奈の鼻唄交じりの歌声が、公園の霊を浄化させただなんて。そもそも偲は、出来の悪い小説じゃあるまいし、そんな戯言を信じてなかった。
「信じてもらおうとは思ってない」
あっさりと匠は言った。
「ただ、北原莉奈から目を放すなとは言われてる。俺もその意見には同意した。そんなわけでよろしく」
葬儀屋と言われて納得してしまったのは、黒いダブルスーツに黒いネクタイ、そして左手首にブレスネットのように数珠をしているせいだ。
西野匠は、天野優が一目見たらブラックアイズにスカウトしそうな美男子だ。恰好が業界人していないだけで、ビジュアル系のアーティストで十分通りそうなくらい綺麗な顔をしている。
もっともそのくらいのインパクトがなければ、この大ぼけの莉奈が顔を覚えてるはずもない。
「莉奈はそれでいいの」
何でこんなこと訊かなきゃならないのかと苦く思いながら偲は言った。
「構わないわ」
あっさりと莉奈は同意した。
「あんたね。いくらなんでも警戒心なさ過ぎだよ。この人が嘘をついてないって保証ないでしょう。それとも敬一パパから何か聞いてるの」
偲の目の前に、名刺が突きつけられた。
「素姓を確かめてくれ」
怒りもせずに匠は告げた。
白い名刺には北原系列の葬儀社の名前と住所、西野匠の名前と肩書きが記されていた。偲は鞄の中から携帯電話を取り出すと、ブラックアイズの坂田を呼び出した。簡単に状況を話すと、坂田はすぐにかけ直してきた。
『その名刺、本物です。西野匠は間違いなくKCSの一級葬祭士で、裏の仕事の話も事実です』
「ありがとう」
信じがたいが、ブラックアイズの調査が間違えるはずはない。ましてや北原の子会社の話だ。偲は引き下がるしかなかった。
「レコーディングには支障のないようにする」
「当たり前よ」
偲はそれだけ言うのがやっとだった。
金髪碧眼のドラマーが楽しくて仕方がないという表情でドラムセットの最終調整をしている。ヘンリー・L・チャベス。現在パリ在住のアメリカ人。ドラムスとパーカションの他、フルートやマリンバもこなし、リードボーカルも取る。
「偲も、莉奈も大きくなったね。僕のこと覚えてる?」
「うん、ハルは変わんないね」
莉奈が軽やかに笑う。ハルはヘンリーの訛が、そのまま愛称になっている。
その隣では、キーボードの城に囲まれたリーダーのジョニー・芳田が、鍵盤の音色をチェックしてた。
「聞いたよ。莉奈、デビューするんだって。そのうち、一曲ね」
「ありがとう。ジョニーさんには頼みあるの。アルバムにジョニーさん、ラブ・イズ・ジャーニー、日本語に直して入れたいんだけど」
「あの曲ならシュンが昔、莉奈に歌わせるって詞をつけてたよ。ほんと、最後まで面倒見のいい男だよな。いいよ、ジョニーさんが、莉奈用にアレンジしてやるから」
そしてギターの高見正志は言葉少なく少女二人を歓迎した。天才ギタリストとして知られること男は絵心もあり、昔、二人とも似顔絵を書いてもらったことがある。
「俺も、リーダーと一緒に、莉奈のレコーディングに駆けつけるから」
「高見だけ連れてくのかい。どうせならバンドで録っちゃってもいいじゃない。どうせ僕らの曲なんだから」
と長身のハンサムガイが笑う。ベースでリードボーカルも熟すクリストファー・ブラウン。日本語が流暢なのは、母親が日本人の為だが、堀の深い顔立ちのどこをとっても外人である。
「だって由之君」
「僕に異存があるわけはないだろう。さて、お嬢さん方、懐かしの対面が済んだら、楽譜に目を通して」
ラスト竹本由之、この日米混合バンドのフロントマンでリードボーカルだ。
リリックと言う名のバンドは七年前、仕掛け人の神沢俊広の死に殉ずる形で解散した。
今回は神沢の没後八年目のイベントの為に一時的に復活する。莉奈と偲が参加するのはその中の由之の曲のコーラスだ。
偲はともかく莉奈はプロデビュー前なので、シークレットの扱いになる。もっとも、プロダクションの方で適度に噂を流すようだが。匠が見た莉奈の隠し撮りもその動きの一つだろう。
「ねえ、このスタジオって、出るの」
両手を力なく前に出してそのまま手のひらを垂らした偲の言葉に、由之はあっさりと答えた。
「噂は聞いたことはあるけど、見たことはないな。まあ、僕はそういうの見えない体質らしいし、でもクリスがいるから大丈夫だろう」
クリスの胸に下がっている十字架は単なるアクセサリーではない。リリック解散後に、宣教師となって今ではベーシストというよりそっちが本業になっている変わり種だ。
「それに、シュンも神主の資格あっただろう。その手の心配をしたことはなかったな」
早世した神沢俊広の実家はこの街では知らないものがいない神宮だ。
「莉奈が歌えば、それで済むよ。僕が払うまでもない」
クリスが簡単に言ってのけた。
「天使の歌声に敵う霊なんてそうはいない」
ハンサムなベーシストはそういって、初見にも拘らず、正確にメロディーをなぞって口遊んでる莉奈を振り返った。
邪気のない歌声だと偲も思う。莉奈はけして天才的な歌い手ではない。声域も三オクターブがぎりぎりだし、声も細い。
ただ、ボーイソプラノにも似た、聖歌隊のようなの歌声の持ち主だ。
莉奈が歌手になると決まった時、偲は悩んだものだった。この歌声が金銭でやり取りされることに、どうしても納得が行かなかったのだ。
当の本人はきっとそんな偲の悩みすら思いつかないだろう。昔から、歌っていればそれだけで幸せだった。それだけは偲にも否定はできなかった。
唯一の部外者は、スタジオのドア付近の壁に背を預けて、半ば目を閉じるようにして立っている。本来無口な男らしく、こちらが必要だと考えたことでも、答えてもらえるのか不安が過る。
「偲?」
由之が声をかけた。
そう、今は歌に集中しなきゃ。
偲は譜面に目を落とした。
天使の声を持っている莉奈には叶わないが、偲とて、人気絶頂のボーカリストだった叔父の歌を子守唄に成長している。
シュンこと神沢俊広も、偲を可愛がり、莉奈と一緒にピアノの手解きをしてくれた。音感は莉奈に負けはしない。
「じゃあ、試しに合わせてみようか」
由之のリードボーカルが偲の耳をくすぐる。
一番大好きな歌声。その声に自分の声を合わせているうちに、偲はいつもの自分に戻るのを感じていた。
レコーディングは何の問題なく終わった。
「バケモノ退治は出来たの?」
メンバーが自らの楽器を片付けにかかるスタジオの隅で、煙草に火を付けていた黒づくめの男に近寄って、偲は言った。
「ああ」
信用できないとありありと顔に出している少女に、匠は短く返事をした。それから、内ポケットから塩を取りだす。
「清めの塩だね。その必要もないと思うけど」
黒髪のベーシストがケースに仕舞ったベースを肩から下げながら言った。
「スタジオならどこにでもいる雑霊の気配が消えた。久しぶりに莉奈の歌を聴いたけど、相変わらず大した威力だ」
当の莉奈は驚いた顔でクリスを見つめている。
「そうなの?」
「クリスが言うならそうなんだ」
さすがの偲も生まれた時からの付き合いのベーシストの言葉は信用するようだ。
その間に、匠は鬼門の方角に塩を撒き終えていた。実際、念の入れすぎだと思わなくもない。だが、莉奈の傍にいる口実としてのパフォーマンスとして必要な行為だった。
「お嬢さま。お迎えに上がりました」
楽器の搬出でごった返しているスタジオのドアから、運転手の坂田が顔を出した。
今日は自ら莉奈の運転手を買って出たが、本来の役割は北原家の執事だ。自宅が完全に空になる時だけ、こうして莉奈に付いて来ている。
坂田は西野匠の姿を認めると、軽い会釈とともに歩み寄った。
「ブラックアイズを束ねております坂田と申します。お嬢さまの付き人をなさるようですね。宜しくお願い致します」
シルバーグレーの紳士は匠に名刺を差し出すと深々と頭を下げた。
「KCSの西野です。こちらこそご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します」
スタジオに現れて以来、ここまで匠がきちんとした言葉遣いをしたのは初めてだった。
「坂田さんって、凄いのね」
そう呟きながら、匠が坂田に手渡した名刺と同じモノをポケットから取り出して、偲はじっと見つめた。
「そう、そんな人が莉奈の傍にね」
天野優こと北原優子夫人は、少女めいた声でそう言った。
まだスタジオでの作業があると言う叔父と別れて、偲は莉奈とともに北原家にやってきた。築年数こそ古いが定期的なメンテナンスをしっかり行っているせいで、機能・外観ともに周囲に林立する新しいマンションと全く劣らない、高級高層マンションの最上階に北原家はあった。
三人が帰るのと時を同じくして、優子は自分専属の出版エージェントである水原玲の車で打ち合わせから戻ってきた。玲は優子を送ると、自宅へと戻っていった。今では、河口医院の医院長夫人の顔も持っている彼女だが、相変わらず男にしたいようなハンサムな顔立ちをしている。
「って、優子ママ知らなかったの?」
噛み付くように言う偲に優子は笑った。
「余程気に入らなかったのね。名刺で顔を見る分には中々のハンサムじゃないの」
「無口で陰気な男よ。何に考えてるか知れやしない」
「莉奈はどうなの?」
制服を着替えて戻ってきた娘に優子は訊く。
「一度、公園で見たことがあるの。ブラックアイズの新人さんかなと思ったけど、何か変なことしようとしてたし、クーペで迎えに来た藤原さんは知らないって言うし」
「なんで、そんなとこ行ったのよ」
「美夜ちゃんの家、円山だって言ってたし、一度も行ったことないし、たまには自分の足で探してみようと思って」
歩き疲れて仕方がなく、迎えの車を呼んだのだろう。莉奈は母親に似て、天性の方向音痴だ。
どうせ、目に付かない位置でブラックアイズが警護しているとはいえ、夕暮れの人気の消えた住宅地であの得体の知れない男と莉奈が二人きりだったと思うと、偲はぞっとした。
「それで、美夜の家は見つかったの?」
佐橋美夜は偲と莉奈の中学校の友人だ。肩を過ぎた辺りで切り揃えたセミロングの髪と大人っぽい顔立ちをもつ美女で、ここにも何度も来たことがあるが、そう言えば美夜の家に行ったことはなかったかも知れない。
「藤原さんが見つけてくれたけど、美夜ちゃんいなかった」
その時間なら、美夜は街中で遊んでいるはずだ。学校ではわりに真面目な子だが、夜毎街に繰り出していると最近悪い噂が絶えない。
「そう言えばこの頃美夜ちゃん来ないわね。元気なの?」
暢気に優子が訊いた。
「元気です。美夜ならそのうち顔を見せるわ。問題は、あの男よ」
「偲は匠君が嫌い?」
莉奈が真っ直ぐな視線を投げる。
タクミクンって誰だろうと、一瞬考え込んだ偲が西野匠のことだと思い当たり呻いた。
「私は偲が言うほど悪い人だと思えないの。確かに、怖そうな人だと思うけど」
「あの男がこれから仕事がある度、付きまとうのよ」
「同じ付きまとうと言っても、彬とは違うわ。煩く口を挟んだりしない。そうだ、彬は?」
「一度お帰りになられて、お出かけになられました。試験が近いので図書館に行くと」
家に帰るなり、執事となってみんなにお茶を煎れていた坂田が答えた。
北原家の跡取息子である彬はこの四月から偲達と同じ中学に上がった。下手をするとアイドルデビューが決まった姉よりも整った顔立ちと、細身だが均整の取れた体つきをしていて、小学校時代から既に[クールな王子さま]の異名を持ち、クラスの女の子の視線を釘付けにしている。
しかしながら、肝心の彬はたった一人の姉のナイトを自認している。特に歌手デビューが決まって以来、口うるさく付きまとっているので、さすがの莉奈も少々閉口気味だった。
「匠君のこと彬には言わないでね、ママも偲もそれに坂田さんも」
「時間の問題だと思うよ」
呆れ顔の親友に莉奈は必死な形相で言った。
「それでもいいの」
優子はそんな娘の様子を見ながら、自分で煎れるよりも余程上手に注がれたダージリンを満足そうに口に運んだ。
「一応、敬には訊いてみるけど。坂田さんはどう思う?」
会話の邪魔にならないように、お茶のお代わりを用意していた執事は、ゆっくりとした仕草で振り返った。
「KCSの一級葬祭士のレベルは、他社に引けを取るものではありません。西野匠は特に立ち振舞いの優美さで最高の得点を得ています。それは一朝一夕に身に着くものではありませんから、茶道の心得があると思われます。確かに人当たりの面では多少取っ付き難いかもしれませんが、二十五歳にしては落ち着いていると思います」
「ブラックアイズ隊長として莉奈の警護を任せられると」
偲の言葉に坂田は穏やかに笑った。
「西野は単なる付き人です。我々は西野を含めて、今後とも莉奈お嬢さまを、誇りを持ってお守りいたします」
偲はやっと安心したように微笑んだ。
ブラックアイズの目が光っているうちは、莉奈に身に危険はないだろう。
莉奈が西野匠をどうやらえらく気に入ったらしいのは気にかかるが、しばらくは静観するしかないだろう。
「偲ちゃん、由之君今日、遅いんでしょう? ここでお夕飯食べるわよね。私、今日は仕事ないから好きなもの作ってあげるわよ」
優子が自分のカップをテーブルに置いて立ち上がった。
「じゃあ、お手伝いします」
優子の手料理はどんなレストランよりも偲の舌に合っている。写真だけでしか母親を知らない偲にとって、優子は母親代わりだった。
由之のことを莉奈が『由之君』と呼ぶのも、二人が姉妹同然に育ったせいである。
「莉奈も手伝うでしょう?」
親友を振り返ると、やっと機嫌を直した偲をほっとした顔で見つめていた。
「ママ、シチューにしよう。偲、制服脱いじゃいなよ」
「あらあら偲ちゃん、着替え、奥の部屋にあるから着替えてらっしゃい」
最近はそうでもないが、由之がツアーに出かける時など、偲を預かるので、普段着もこのマンションには置いてある。
「じゃあ、着替えてきます」
「ちゃんとエプロンもするのよ。莉奈も」
母親の言葉に莉奈が舌を出す。玄関で音がしたから、彬だろう。
北原家に平和な夕食時が近づいていた。
同じ頃。
「九時にいつものところで待ってる」
少女のPHSにメッセージを入れると、西野匠は携帯を内ポケットに仕舞うと、代わりに煙草を取り出した。
今夜、匠が莉奈の知らない名前で抱いて眠る予定の少女の名は、佐橋美夜。
運命の糸が絡み合いだしたのを、まだ誰も気付かないまま、大都会に夕闇が降り始めた。
Fin