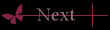「西野さん、館長からです」
弔問客の多さに比例して鳴り響く、葬儀会場への道案内の電話対応に追われている事務職の女の子が、電話も取らずにパソコンで怪しげなページを見ている葬祭部員二名を軽く睨みつつそう告げた。
彼女はその外線を保留にして、すぐ次の電話を取り上げる。
「西野です。……はい、わかりました」
匠が受話器を置くと、すぐにその電話が鳴り出す。間髪を容れずにそれに出て、道案内の対応を済ませると、事務所に入るなり脱いでその辺のパイプイスの背に掛けた上着を着込む。
そのままドアに向かう匠の背に、中山が声をかけた。
「オヤジさんなんだって、裏稼業の打ち合わせか?」
それには答えず、ただ片手だけを挙げて匠は事務所を出た。
それ自体が珍しい行為なので、中山は目を見張って閉ざされたドアを見た。
葬祭部平岸事務所の二階にKCSの本社の事務所があり、墓石部と冠婚部、衣装部、そして顧客管理部を統括する事務を司っていた。
葬儀会場の正面玄関から出入りができる葬祭部の事務所とは、外からの出入り口自体が違うので、二階廊下の右突き当たりの壁にあるドアが関係者用通用口になっている。
しかし、匠はそこへは向かわず、階段突き当たりを左に折れた一番左端の、僧侶控え室の方に歩いていった。普段は使っていない布団を仕舞っているせいで、布団部屋と呼ばれている三畳の和室だ。
――北原社長が、布団部屋でお前を待っている――
携帯から事務室に外線を入れた館長は、それだけを告げると電話を切った。匠の返事は聞こえたはずだが、電話を受けた本人は内心半信半疑だ。
六時からの葬儀のため、二階にはほとんど人がいない。
格子戸から和室の玄関を覗き見ると、一目でブランド品とわかる紳士靴が戸口の方を先にして綺麗に並べて置いてあった。
覚悟を決めて匠は靴を脱いだ。
「西野です」
声をかけてから、作法通りに正坐になって襖に手をかける。
「どうぞ」
明るい声が襖越しに聞こえた。どこかで聞いたような男の声。けれど、館長の声ではない。
「失礼いたします」
襖を開け、膝の向きを変えて襖を閉める匠を、男は感嘆の表情で眺めた。
「さすがに一級葬祭士だね。私にはとても真似出来ない」
窓辺に立って、夕闇に沈む五月の空を眺めていたらしい男は、床の間を背に胡坐をかくと、匠にも腰を降ろすように告げた。
社内VTRによる社長訓示よりもむしろ、巷を流れるTVCMで馴染みの男が、匠の前に腰を降ろしている。四十半ばの年齢の筈だが、どう見ても三十代後半にしか見えない。精悍な顔つきはCM用の化粧などではなく自前だとわかる。
「忙しい中呼びつけたりして済まなかった。北原敬一だ」
内ポケットからバーバリーの名刺入れを出し、中から抜き出した一枚を卓上に滑らせ、北原はやんちゃな笑みを零した。
「我が国の慣習では目上の者が目下の者に名刺を渡したりするのは、礼儀上反するらしい。百年前、ある県の知事に当選した人気作家が、自分のメールアドレスが印刷してある名刺を渡したところ、古参の県幹部に目の前で破られた。その名刺は、大切な一握りの友人や緊急を要する取引先の役員にしか明かすことのない、私のプライベートの携帯番号が印刷してある。出来れば、破らないで欲しいな」
今度こそ心底驚いた匠は世界のKITAHARAを背負って立つ青年実業家を見つめた。
「子会社の一社員に過ぎない俺に何の御用ですか?」
北原は湯飲みの蓋を開けて、ひとくち口に含んだ。
「私の娘が歌手デビューをするという噂は耳にしているかい」
匠はこっくりと頷いた。
「八年前に四十の若さで亡くなった親友の遺言でもあるし、娘が心底望むなら好きなようにさせてやろうと思ってる。そこで、君を娘の傍に置こうと思う。いわば付き人だな」
プライベートの名刺を貰った時も驚いたが、今度の言葉は悪い冗談としか思えなかった。
北原も匠の表情を見てそう取ったのだろう。苦く笑いながら、言葉を紡いだ。
「君は裏の仕事でも優秀だと聞く。私はどうもそういうことに疎いのだが、見る人が娘を見ると、娘の纏う気は綺麗過ぎて、一旦悪いモノ? そいつにとり憑かれると厄介らしい。芸能界は魑魅魍魎が跋扈すると言う」
世界を相手に商売をする一流のビジネスマンにしては荒唐無稽な話だ。匠は仕事柄そういうモノがいることを、経験的にわかってはいるが、普通の人間が聞いたら冗談と聞き流すか、どうかしていると思うかのどちらかだろう。
けれど、中山がネットで見つけた写真の中学生に良く似ている、夕暮れの公園で見かけたあの少女が本当に北原莉奈ならば、ありえない話ではない。
「俺を指名するなら、行状についてもお耳にしているでしょう?」
パソコンでアクセスしながら中山が口にした匠についての話はあながち間違いでもない。
「俺がお嬢さんの悪い虫になるとは思われないのですか」
北原の眼光が一瞬険しくなり、刺すように匠の目を射た。
匠は恐れを感じて反射的に目を伏せた。
「吸ってもいいかな」
匠が頷くと、マルボロを内ポケットから取り出し、北原は煙草の箱に入っていたライターで火を付けた。
「無論、君の調査はしている。プライベートであまり誉められた行為をしていないことも調査済みだ。 それについては双方合意とのことだし、女性に対する守備範囲が広いと目をつぶろう。警察沙汰は困るが、そんなドジも踏みそうもないし」
と、一息入れるように煙草を咥える。煙草の先が赤く燃え紫煙が真っ直ぐに昇っていった。
「これでも、人を見る目には多少なりとも自信があるつもりだ。君はつまらない感情で、人生を棒に振るようなことはしまい。それに私は娘を信用している。けして親を泣かせる真似はしないとね」
匠はしばし考え込んだ。
「莉奈はデビューするとはいえ、基本的には学業優先だ。活動は放課後と休日になる。幸い私には、娘に芸能界で稼いでもらわずとも困らないだけの生活力はあるし、君が裏の仕事を続けたいと思うなら、この依頼に支障のない範囲でしてもらって構わない。篠原にも、緊急要員として葬儀が立て込んだ場合に使えるようにして欲しいと頼まれてるし」
「社長のプライベートのボディガード部隊は、他からスカウトが来るほど、優秀だと聞いていますが」
「生憎、ブラックアイズの訓練項目には、バケモノ退治は含まれていないんだ。娘のプライベートの行動まで見張れとは言わないし、仕事中も警護はさせる。ただ、所属事務所と打ち合わせて、娘のマネージャーは兼ねてもらうかもしれない。その方がいいだろうし」
実質的にはタレントの付き人に当たる仕事を熟さなければならないだろう。葬儀屋になったのは自分の意志だが、一生続けていきたいと思っているほど、好きな仕事ではない。
「返事は今すぐに?」
北原は苦笑を帯びた笑みを浮かべた。
「私としてはすぐ欲しい。君と会うためだけにイギリスから飛んできたんだ。話が済んだらすぐに千歳に向かわなければならない」
「お引き受けします」
匠はそう答えていた。
――あの少女にもう一度逢いたい。
一目惚れとは思わない。
それに恋愛感情を持つには厄介すぎる相手だ。
北原は安心したように匠の手を握った。
「娘をお願いします」
莉奈は、神沢俊広と北原敬一夫人である天野優との間に産まれたと口さがない世間が噂をしている。けれど、こうして頭を垂れている北原は娘が可愛いだけの父親だった。自分の血を引いてない娘をここまで愛せるはずはない。
「タイムリミットだな」
ロレックスの腕時計に目を落として、北原は言った。その仕草を見つめていた匠の表情が微かに驚きを帯びた。
「篠原が不服そうな顔をした理由にようやく合点が行ったよ。あいつは無駄な金の使い方はしない。君は高給取りのようだ」
匠の腕に嵌められている全く同じモデルの腕時計に視線を向けて、北原は言った。
それに軽く目を伏せただけで、匠は立ち上がり、玄関へと向かう北原を送るために襖を開けた。先に靴を履いて、靴箆を差し出す。
「君はもう、ピアノは弾かないのかい?」
靴を履きながら、北原はふとこんな言葉を口にした。
或いは今まで交わされた会話の中で、匠に取っては一番思いがけないものだったかもしれない。それはまた北原の言う調査が完璧に近いものだという裏付けでもあった。
「はい」
躊躇もなしにそう声に出して答える匠に、北原は実に残念そうな顔をした。
「……そうか。あとのことは追って連絡する」
格子戸を開けて北原を送り出した西野匠は、自分の身に起きた出来事を十分に理解できないままに、その背中を見送った。
ただ自分の運命が大きく変わろうとしていることだけは、ひしひしと感じていた。