小学校の音楽の時間には、何の疑問も無く、横に長い<や>という記号があることを学んだ。しかし、普段の授業では、簡単な歌を歌うのがせいぜいで、長い<や>が、実際にどのようなものであるかはよくわかっていなかったし、壁にかけられているバッハやモーツァルトが、実は、これらをほとんど使わなかったというのは学ばなかった。改めてそのような話題にめぐりあった時、「え、本当ですかそれは」と思ったが、記憶を探しても、モーツァルトでは、長い<を2箇所程度しか思い出せなかった。
つい先日、crescendo(長い<、クレッシェンド。音が徐々に強くなる。略して、cresc.) と diminuendo (長い>、ディミヌエンド。音が徐々に弱くなる。略して、dim.) について考えていた。そのことが書かれた論文があって、ダイナミックス(音量の起伏)はベートーヴェン音楽の根幹になるものだと結論づけていたが、実際に数えてみた。交響曲第9番(1824)の第1楽章(約16分)における個数は、こうだ.
cresc. 23個
dim. 12個
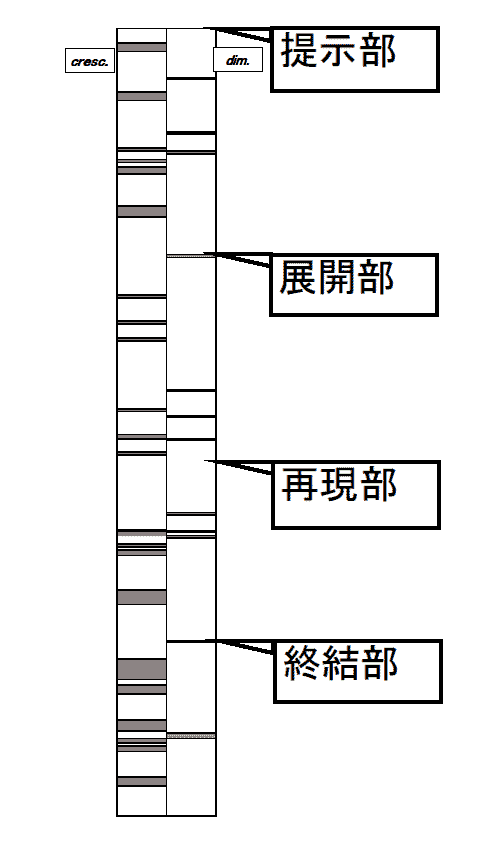
もちろん、1小節で終わってしまうのもあれば、延々16小節ほど続くのもある。面白そうなので、その分布を図にしてみたら、こうなった。上から始まって下で終わる、全547小節。左側が、cresc.、右側がdim.で、縦が長いほど、長いスロープを作っている。見てのとおり、縦の幅が広いところは、全てcresc.だ。dim.は、短い。音量が下がるだけでなく、運動エネルギーまでもが減るようなdim.を、ベートーヴェンはほとんどやらないのである。
一寸話は変わるが、diminuendo と decrescendo は、同じように「音が徐々に弱くなる」という意味だが、あちらの言葉のニュアンスがわからない。きっと、微妙な違いがあるのだろう。ベートーヴェンでは、decrescendoという言葉を、とんと見たことが無い。見つけられなかっただけかもしれないが。と思ったが、第2交響曲の第3楽章にあった。
さて、このままではいけないので、大先輩であるお二方の作品で、円熟している交響曲からデータを取ってみるとこうなった。ちなみに、1楽章を抜き出して探したのではなく、全4楽章で探してみたのだ。
モーツァルト 交響曲第40番(1788)、第41番「ジュピター」(1788)
cresc. 2個 3個
dim. 0個 0個
ハイドン 交響曲第100番「軍隊」(1794)、第104番「ロンドン」(1795)
cresc. 7個 2個
dim. 5個 2個
どうです、少ないでしょう。音がだんだん大きくなるなんて、どこにでもあると思っていたのではありませんか?
これではあまりにも少ないので、図にすることもできない。なんと、ハイドンとモーツァルトの交響曲あわせて4曲2時間に比べて、ベートーヴェン「第9」のたった16分のほうがcresc.、dim.の数が多い。少し調査を進めてベートーヴェンの交響曲第1番(1800)を見てみると、冒頭から2分も経たないうちにcresc.を7個も使っている。「ロンドン」初演から5年しか隔たっていないにもかかわらず、この違いはどうだろうか。
単なる個数でもこうなのであるが、特にcresc.は、長さも全く違う。モーツァルトやハイドンの場合、これらの記号はせいぜい2小節にまたがる程度のものであるが、ベートーヴェンは4小節程度はあたりまえ。長いと16小節にもなる。
こういうことは、現代のように、いつでも好きな音楽を聴ける環境で何度も聴く人なら、すぐにわかることなのであるが、当時は、どのように捉えられたのであろうか。
このあたりに、モーツァルトやハイドンの、いや古典派の、すっきりとした性格が現れているのだろう。
ちなみに、ベートーヴェン以後はどうだろうかと調べてみた。シューベルトの交響曲「ザ・グレート」(1828)では、第1楽章のみでも20個以上のcresc.がある(シューベルトは書き方がいい加減なのでクレッシェンドかどうかわからない記号がある)。また、延々16小節にわたるcresc.があるところを見ると、さすがにベートーヴェンをよく見ているというか、手本にしようとしているのではないかと思ってしまう。
もうひとり、ベートーヴェン直後に有名な作品を書いた人物にベルリオーズがいるが、もうご存知の通り、ヘンタイの部類に入る作曲家なのであまり比較にならないが、ダイナミックスの幅はベートーヴェン以上だ。幻想交響曲(1831)の最弱音は、それこそ聴こえないくらい。最強音は、大爆発。当然、cresc. や dim. は、そこらじゅうにある。
このようにダイナミックスに幅のある表現があらかじめ設定されていると、たとえ楽譜に何も記号が書かれていなくても、いろいろとニュアンスを付け足しやすい感じがする。
かといって、元々の楽譜に綿密に計算されて記号が配置してあるため、その流れを考えないで余計に付け足すと、それがかえって不自然になって、聴いていて妙に気になってしまうことになる。私も、いろいろ聴いていると、突然、あるはずのない所にcresc.やdim.があって、頭の中でつまずいてしまうことがあった。これがこの指揮者の表現なのかと思いつつ、自分の頭の中のイメージと重ねてしまう。この解釈が良いか悪いかといえば、誰の頭の中においてもつまずかせずにしっかり聴かせてしまうのであれば、良い解釈をしていると考えていいのかもしれない。
思えばフルトヴェングラーに代表される20世紀の巨匠や、指揮者ハンス・フォン・ビューローやワーグナー、マーラーを始めとする、19世紀の(指揮者という意味での)巨匠も、ベートーヴェンの交響曲にことさら思いを寄せてあれこれ解釈を重ねてきたのは、19世紀を通して管弦楽団が巨大になってきたことと、ベートーヴェンの、このような音楽のダイナミックス上の幅の広さがあってこそのことだろう。もし彼の音楽に、クレッシェンドやディミヌエンドがほんの少ししか与えられていなかったとするなら、いかにベートーヴェンが音楽の展開をうまくこなしたところで、せいぜいモーツァルト程度の対応、つまり、ことさら人生に関係づけたいかのような解釈には、ならなかったんじゃないか。あるいは、そのような時代が長く続いたんじゃないかと思う。
このダイナミックスの幅の広さは、その後の音楽の発展には不可欠だった。ベートーヴェンは、主題の展開能力は空前絶後であるし、管弦楽法(楽器の使い方)も当時としてはピカ1であったが、じつは、ヨーロッパの音楽をロマン派への道を開いた根源の力というのは、そのようなことではなくて、このダイナミックスの表現が、計画的に、こと細かに、ドラマを創るために設定されていたことにあったのだろう。ここで、なぜ「ロマン派」という言葉があてがわれたのか私は今もってわからない。おそらくロマンティックの語源に意味があるだろうが、わかりやすく言い換えてみると、音楽は、ベートーヴェンをもって「ドラマティック派」になった、というようなところだろうか。おそらく、cresc.やdim.を慎重かつ大胆に使おうとする作曲家が、ベートーヴェン以外でもあちこちで出現し始めていて、徒党を組んでいたわけではないだろうが、一派を形成していたような感じだ。こうして、シューベルトやベルリオーズもが、幅広いダイナミックスを持つ音楽を書いていった。他にも何人もいたことだろう。
こうなったことは、ピアノの発展も理由のひとつだろうか。バロック音楽の鍵盤楽器はチェンバロだ。弦をたたくのではなくて、はじくので、鍵盤を強く押しさえすれば音が大きくなるというものでもない。だから、cresc.やdim.は、ありえない楽器だった。18世紀末、そこに現れたピアノは、大きな音も小さな音も出るからと、ピアノフォルテとかフォルテピアノと呼ばれたくらいだ。おそらく一番身近な鍵盤楽器の音量の幅が増大することで、作曲家の頭に、fやpの数が増え、cresc.やdim.などの記号が大きな位置を占めたのだろう。
こうして、ヨーロッパの音楽は、ダイナミックスの幅が物凄く広い、大管弦楽の作品を多く生むことになった。世界中のどんな音楽でも、これほど音量の起伏が大きなものは、他に無いはずだ。
(2007.9)