舞台配置
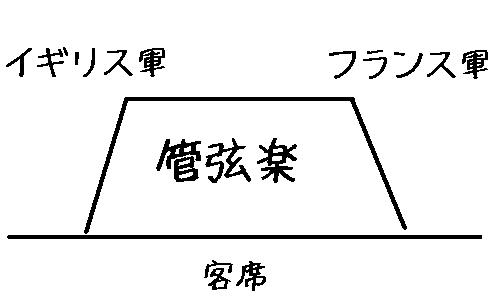
イギリス軍は、舞台裏左手、フランス軍は右手になる。イギリス軍が西から攻めていったということなのだろう。
第1部「戦争」
単発講座「戦争交響曲」(改訂:2009/5/9)
ここでは、今でこそキワモノ扱いであるが、存命当時は超有名になってしまっていた歴史的な描写音楽「ウェリントンの勝利、または戦争交響曲」について、イギリス、フランスの両軍の軍備紹介をしよう。
舞台配置
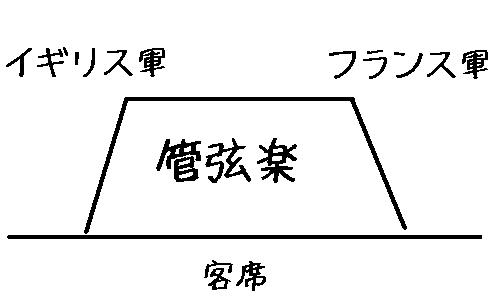
イギリス軍は、舞台裏左手、フランス軍は右手になる。イギリス軍が西から攻めていったということなのだろう。
第1部「戦争」
舞台裏左手 |
舞台裏右手 |
管弦楽 |
|
曲の構成:
イギリス(舞台左)
小太鼓による、イギリス軍登場。
トランペットによる号令。
ルール・ブリタニア演奏。以上、変ホ長調。
フランス(舞台右)
小太鼓による、フランス軍登場。
トランペットによる号令。
マールボロ行進曲演奏。以上、ハ長調。
まず、両軍が順に登場する行進曲。イギリス軍行進曲(ルール・ブリタニア)、フランス軍行進曲(マールボロ)で、舞台裏の左右に配置された各吹奏楽団が演奏する。
イギリス軍は変ホ長調、フランス軍はハ長調が象徴している。そのため、舞台の管弦楽では、2つの調にホルン各2個を、トランペットを各1個を割り当てている。
左側から小太鼓のリズムに乗って、イギリス軍の信号ラッパが鳴る。そして、ルール・ブリタニア。次に、右側から小太鼓のリズムに乗って、信号ラッパ。そして、マールボロ。
イギリス軍 |
フランス軍 |
管弦楽 |
|
Aufforderung 両軍戦闘準備
両軍のトランペット吹奏
Schlacht 戦闘
・Allegro ロ長調 4/4 - 変ホ長調
さっそくいきなりの全面攻撃。前置き無し。双方、派手に大砲と小銃が撃ちまくられる。
左右の各吹奏楽団からは、太字で書かれた楽器が以上のように参加する。トランペットは信号ラッパだ。昔は、大太鼓が大砲の役目を果たしたが、現代では実際の大砲の音を録音するか、波形合成された電子音が使用される。マスケット銃は、右手でくるくる回すと「カカカカ!」と音が出る木製の楽器(っていうのだろう、やはり)が使われるが、本物の銃の録音もあるはずだ。
・Meno Allegro ハ長調 3/4
音楽としては場面転換しているが、戦況が実際にどう変わったのかはわからない。単純な描写とはいいながらも、各楽器群は凝った動きを示している。末尾6小節はベートーヴェンらしい場面転換を示し、次になだれ込む。
ここまでの管弦楽では、なんとも珍しいことにティンパニがまだ出てこない。
Sturm-Marsch
突撃
イギリス軍の小太鼓がフランス軍に迫る。全軍突撃なので小太鼓は、やはり複数が必要。譜面上はどの楽器も多いほど良く、小太鼓なども左右各1人である必要は無い。
・Allegro assai 変イ長調 2/2 - イ長調 - 変ロ長調 - ロ長調 - 変ホ長調
イギリス軍が総攻撃を開始。小太鼓が推し進める力と半音単位で上昇していく調は、進軍状況を示すのだろうか。
・Presto 変ホ長調 2/2 - ニ長調
かなり敵地に侵攻できた。fffの指示も見える。この部分の中ほどから、フランス軍の大砲は静かになってしまう。「隊長! わが軍は圧倒的であります!」 そして音楽も、静かになっていく。
・Andante 表記上はロ短調(実際は嬰ヘ短調) 6/8
戦闘の終結とフランス軍の敗走。硝煙がたなびく戦場の荒地。マールボロ行進曲が細切れになって消えていく。負けてしまったが、装飾音符がいまだくっついているところがご愛嬌だ。
第2部「勝利の交響曲」
管弦楽 |
Sieges-Symphonie
勝利の交響曲
・Intrada: Allegro ma non troppo ニ長調 4/4
ファンファーレによる導入部。トランペットが4本(以上)なので、この後の部分とともに、ベートーヴェンにしては珍しいほど華やかに感じられる。
ここでやっとティンパニが現れる。ホルン、トランペットはニ調になる。
・Allegro con brio ニ長調 2/2
祝祭気分を盛り立てている。
・Andante grazioso 変ロ長調 3/4
ゴッド・セイブ・ザ・クイーンの提示。戦勝国であるが、いたって落着いた雰囲気での登場。さすが歴史ある王侯貴族というところだろうか。
・Allegro con brio ニ長調 2/2
祝祭部分の再現。
・Tempo di Menuetto Moderato ニ長調 3/4
ゴッド・セイブ・ザ・クイーンの変奏。小節単位の強弱の交替が何を意味しているのか、よくわからない。
・Allegro ニ長調 3/8
ゴッド・セイブ・ザ・クイーンの主題によるフガートとフィナーレ。さすがに、国歌を大々的に鳴らしてのこけおどし的なコーダにはなっていない。節度を持った終わり方だと思う。
ここで注意しておきたいのは、この戦争交響曲の作曲者も初演時の演奏家も聴衆も、イギリス/フランスのどちらでもないというところだ。だから、コーダでゴッド・セーブ・ザ・クイーンは大々的に演奏されずに、めでたさを単純に示していることで止めているのだろう。
この曲と対比できるのは、チャイコフスキーの大序曲「1812年」くらいだろう。もうご存知の通り、この2曲は大砲を鳴らす曲の双璧である。あちらはフランス対ロシアであったため、末尾で勝ったほうの歌が大々的に聴かせられるのは当然だろう。ただ冷めた耳で聴けば、それが自国の大勝利であってもバカバカしく感じられてしまう。デカく鳴ればいいってもんじゃない。広く聴かれるにはある程度の節度が必要なのだ。
しかしまあ、「1812年」の冗長さに比べて、ベートーヴェンはなんとも単純明快だなと思ったりする。両軍が登場して、いきなり戦闘なのだ。そして、攻めて勝って万歳で終わりである。
一方、「1812年」は大砲の音が登場するまでが長い。確かに緊迫感はあるが、チャイコフスキーらしく延々と楽想を展開する。クライマックスの手前では、だらだら下降する音型が冗長を通り越して約1分(曲全体の5%に相当する)にわたって続くのである。普通はやらないだろ、そんなの。とにかく、大砲を撃ちまくることに徹することができなかったチャイコフスキーの切れ味のニブさがここに現れているようだ。