そもそも第1主題に対して特に第2主題を女性的(ってことは第1主題は男性的?)というような表現で比較しがちな説明は、いつ頃、誰がどういう思いで始めたのだろうか。これもマルクスか? しかし幸いなことに、それほど頻繁にこのたとえ話が見られるわけではない。
実際にその男女の例えの説明に合致してそうな例として、「コリオラン」序曲をあげよう(下例①、上が第1主題、下が第2)。
例①

ベストマッチングな楽想なので、いきおい女性的な第2主題と書きたくなるのもわかるが、勇み足である。
コリンの戯曲「コリオラン」には、実際に勇者コリオラヌスと呼ばれた主人公の妻が出てくるらしい(読んでないが)ので、第2主題を妻に強制割り当てしても一応問題ないように見える。しかしベートーヴェンが妻の存在を意識して第2主題を書いたと明言しているわけではない。うがった見方をすればいいというものでもない。
似たような作品に「エグモント」がある。この劇では恋人「クレールヒェン」が登場する(*1)。しかし「エグモント」序曲の第2主題が女性的とは言い難い(下例②、上が第1主題、下が第2)。
例②
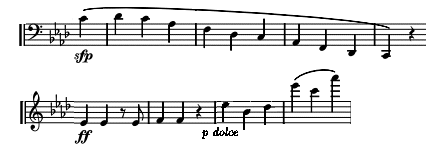
いやいや第2主題の最初の2小節が"ツン"で、続く2小節が"デレ"なのだよと言われたら、そうかもしれないがw
ついでに書くと、「レオノーレ」序曲(第2,3番)の第2主題は、劇中のアリアをもとにしている落ち着いた旋律であるが、歌っているのはフロレスタンという男なのだ。それでは主役のレオノーレ(フロレスタンの妻)が第1主題なのかというと、ご存知の通り、あのエネルギッシュな旋律が女性だというのなら、フロレスタンは妻に牢獄から救われても、後で尻に敷かれっぱなしであることは間違いない。
これまで出た例で考えれば、コリオランはごつい主題かなめらかな主題か。エグモントは陰気か陽気か。レオノーレは快活か落ち着いている(それとも落胆)かという表情の違いでしかない。むしろ、第1主題を男性的、第2主題を女性的としたような曲を探すほうが難しいと思う。
もちろん上の3曲はもともと男女が表現されていてもおかしくない理由があるので、そういう主題の対比になっていてもよい。しかし、純粋な器楽である交響曲やピアノソナタなどに男女の例えを出さなければいけない理由は無いし、2つの主題の対比をどうするかは作曲者の手腕であって、男女に容易に例えられるようなマヌケな曲はこちらとしては願い下げだ。
誰が最初に言ったのか知らないが、第1主題が男性的であることに対して第2主題が女性的なんていうのは、実際の音楽の比率としてかなり少ないはずで、勝手な考えである(*2)。多種多様な混沌に画一化した見方を押し付けるのは、どこでもありがちな話であるが。
さて、ついでに歌劇「フィデリオ」の序曲はどうかというと、こうなっている。

どちらも、なんだかホームドラマのような筋書きしか考えられないような旋律である。
さて、2011年10月2日、NHKで坂本龍一教授の「スコラ」という番組があって古典派の音楽の解説をしていたが、ここでソナタ形式の第2主題は女性的という説明に言及した。言及しただけで重視はしなかったが。
とまあ、それくらいならいいのだが、出してきた例がベートーヴェンのピアノソナタ第1番であるところに演奏例がグレン・グールドときたのだから、知っている人間は何やってんだ、と思ってしまう。
譜面の例は下(2段めと3段めの間で1段分省略あり)。第1主題は右手でポツポツと上昇する。左手は和音が少し。一方第2主題は右手でなめらかに下降。左手はオクターブで持続音。要は下線のある3点の対比が重要であって、女性的なんて関係の無い主題。しかも説明では対比の3点のうち上昇下降の1点のみ言及。おまけにグールドの演奏はスラーを重視せずといういつもの演奏。こんな演奏例を持ち出しては聴いているほうには違いが不明確じゃないですかね。

でもまあ、しょせんテレビなんだし…。そこそこわかっている人しか見ないだろうし…。
では第1、第2主題の違いがあまりにも明確なのはというと、これを持ち出さずにはいられない。ワルトシュタイン・ソナタの第1楽章(2段めと3段めの間でかなり省略あり)。これくらい性格が違う2つの主題なら誰でもわかりますよ。
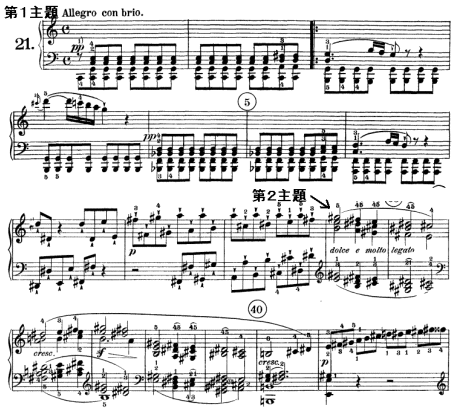
でも、これほど性格が違ってしまうと、この第2主題の手前で減速する演奏家が現れるんですよ。やりたくなる気持ちはわかるんですがね。
*1 劇中の出来事に遭遇した時点の実在のエグモントは年配の男だった。エグモントを若者にして恋人クレールヒェンを配したのは筋書き上の設定である。
*2 「おまえ、女性に何を期待しているんだ」と小一時間問い詰めたい。優しくなめらかな旋律を「女性的」と思うのなら、間違って現実を認識しているに違いないのだから。
(2011/10/23)