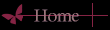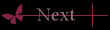青年が初めてその少女を見かけたのは、夕暮れの公園だった。
マンションの狭間にある鉄棒とブランコとすべり台だけの小さな空間。
子供たちはみな帰ってしまった。
もう夜の方が近い時間。太陽の光は西の空に紫色の残照を残すのみだ。
青年は仕事の途中だった。
入口と反対側の車道に商売道具一式を詰め込んだワゴン車を停め、腰の高さほどの鉄柵を乗り越える。正面で錆び付いたブランコが揺れていた。
風が少し強くなった。
五月も下旬というのに風はまだ冷たい。
少しだけ湿った風は雨の匂いがした。
彼は黒いダブルのスーツのポケットからライターと香炭を取り出した。乾いた石を見つけてしゃがみ込んで、香炭を乗せ、風を除けてライターで火を点ける。
降り始めた夜に香炭が赤く燃え出したのを確かめ、焼香を始める。左手首に嵌めているのは翡翠でできた念珠だ。
逢う魔が刻。昼と夜の境が曖昧なこの刻を、昔の人はそう名付けて恐れた。闇の中には鬼や魔が棲むと、誰もが本気で信じていたのは遠い昔の話だ。
そう人々が信じるに至ったのにはそれなりの根拠があると、何故、誰も考えないのだろう。
青年は焼香の香りの中にすっくと立ち上がった。おもむろに両手を合わせ、仕事を始めようとしたその時だった。
風が、運んできたものがある。
青年は思わずその方を振り返った。鉄棒に背を預けた少女の影が見える。
風が運んだのは歌声。
戯れに口をついて出た、古いラブソング。
声を張り上げていたわけではけしてない。
風向きが変わったなら、かき消されそうな歌声だ。
けれど、よく通る澄んだ声。
そう珍しいことではない。人待ち顔の少女が、時間つぶしに人気ない場所で歌を口遊さんだだけ。
青年が振り返ったのは、それが原因ではない。
夕風が運んだのは、それだけではないのだ。
清浄な気だ。例えるなら木漏れ日を揺らす風。小川を渡る風。邪気を祓うのでなく、取り込んで清めてしまうもの。
青年の視線に気づいた少女が照れたように舌を出したのと、白いクーペが公園の入口に着いたのが同時だった。
呼び止める間もなかった。
身軽な仕草で駆け寄ると、少女は車中の人となった。
エンジン音と赤いテールランプだけが、青年に残された。
携帯電話で呼ばれるまで、青年はその場に立ちつくしていた。
その時、青年は少女の名前さえ知らなかった。
耳に残っていたのは少女の歌声。『ありがちなラブソング』という、今は結婚してめったに歌わなくなったアイドル歌手の往年のヒット曲だった。
その噂自体は、西野匠も耳にしていた。
北原の姫君がこともあろうに、アイドル歌手デビューをする。
北原といえば、ビルから家庭電化製品・薬品、果ては航空機やヘリコプターまでを企画・製造・販売・メンテナンス、挙句に回収まで一手に引き受ける世界的大企業だ。
現に彼の表の仕事場であるこの斎場も北原所有の建築物の一つだし、中の機械設備はもちろん、ロウソク・線香に至るまで北原の製品だ。
早い話、北原の手に掛かっていないのは遺体だけではないかとまで言われているのだ。
現社長は北原敬一。自らの企画で自社のコマーシャルフィルムに登場して以来、総理大臣よりも顔が売れてしまった男だ。
令夫人は天野優。こちらは、中堅の女流作家だ。昨今、ミリオンセラーこそないが、少女のような瑞々しい感性で書かれた作品には定評がある。
その愛娘がアイドル歌手デビューしたところで、普通なら話題性こそあれ、驚くことではない。ところがこのお嬢さまは両親の顔がどれだけ売れようが、写真一枚マスコミに出たことがないほど、鉄壁のガードがされていたのだ。
北原が葬儀業界に乗り込んだのはつい最近だが、北原家はそもそも先祖に陰陽師がいたなどとまことしやかに囁かれている、日本でも由緒正しい家柄らしい。
そんな家柄の深窓の御令嬢が、百鬼夜行の魑魅魍魎が蠢く芸能界にデビューするとなると、噂にならない方がおかしい。
西野匠は、国立大学を卒業し、KCS(北原セレモニーサービス)に入社して三年目である。一級葬祭士〜それが今の匠の表向きの肩書きである。
葬儀屋は、確かに様々な人と遭う機会がある。死というのが、不平等な人生で唯一誰にでも平等に起こる出来事である以上、そして葬儀屋が基本的に客を選ばない以上、あらゆる職種並びに人種・性別の死に立ち会うわけだ。
とはいえ、全人口におけるアイドルの密度はかなり低い。故にアイドルおよびその関係者の葬儀を司るなんて確立は自ら低くなる。
よって葬儀屋である西野匠がアイドルと遭遇する場面も少ないわけだ。
たとえそれが自社の社長令嬢であっても、その確立が上がる訳ではない。
北原は日本で五指に数えられる企業グループだ。一介の平社員などは、社長令嬢は無論、社長ですら生でその御尊顔を拝す機会などないに等しい。北原莉奈は当然、匠にとって雲の上のお方であった。
携帯で呼び戻された匠は、待ち兼ねていた同僚に肩を抱かれた。十人いる葬祭部員の中でまだ若いが古株の長身の男は、匠の顔を覗き込み、実に嬉しそうに笑って見せた。
匠は無言で馴れ馴れしく身を寄せる同僚を睨みつけた。
口数が少ない上に、わりに整った顔をしている匠は、無表情で近寄りがたいと、余程親しい人間以外は好んで寄り付く人間はいない。
中山はそんな数少ない同僚の一人である。
反射的に匠の肩に回した腕を反射的に外されたのに気にした様子もなく、中山は含み笑いを続けている。
今日は土曜。賭事には誘われてもけして手を出してはいけないと、懇切丁寧にその態度で教えてくれる同僚に囲まれているおかげで、知らぬ間に匠もいつ馬がグリーンを走らされるかくらいは覚えてしまった。
「馬は今日、買ってない。それどころじゃなかったんだ」
「もう走ったのか?」
何も言わないのに匠の考えを読んだみたいにそう告げる中山に訊きながら、匠は事務所の奥の壁に並んでいるホワイトボードを眺め、それから、その脇に掛かっている順番札に目を移した。
今日の葬儀件数は全部で五件。然程忙しいわけではない。中山の順番は三番だ。
「北原の御令嬢の写真をネットで手に入れたんだ」
確かにそれどころじゃない。中山にとってと言う意味だが、匠にしても買う気のない馬券の話よりはましだ。
「デマじゃないのか」
誰も顔を知らないのだ。偽物が横行している可能性だってある。というより、そっちの方が高い。
「お前、ほんとに何も知らないんだな。本物だろうが偽物だろうが、[北原の御令嬢]の写真自体流れたことがないんだ」
中山の言葉に、匠はわずかに眉を潜める。
噂には聞いていたが、とんでもないガードだ。普通、ネットの情報をコントロールするなど不可能だ。専門の人間を配備しているにしても、そこまでできるものなのだろうか。
「いいか。アイドルってのは顔が命だ。どんなに歌が上手かろうと、スタイルが良かろうが、少なくとも半数以上の男共に印象の残る顔立ちじゃなければアウトだ。まして、父親は役者にしたいようないい男、母親だって、かってアイドル作家と呼ばれていた。例の噂が仮に真実だったとしても、神沢俊広だってJ・POPS界の貴公子と呼ばれた男だ。期待は高まるわな」
「両親が共に美形だからと言って、子供までそうとは限らない」
匠の言葉に中山は鼻白んだ。
「夢のないこと言うなよ。古来[深窓の令嬢]って言うのは美人の代名詞だろうが。見たくないんならいいぜ」
匠は微かにため息を吐いた。まるっきり興味がないと言えば嘘になるが、アイドルデビューすれば嫌でも目にする顔だ。別に今どうしても見たいわけではない。
大体、携帯一本で呼び戻したのは中山の方だった。
「そんなことで呼び戻したのか」
中山は口元だけで苦笑した。
「いくら俺だって、写真一枚で裏稼業中のお前を呼び戻したりしやしない。こっちはおまけだよ。俺はオヤジさんの命令に従っただけだ」
「館長命令?」
そう匠は問い返した。声に訝しさが宿るのは致し方ない。
南平岸にあるここKCS平岸シティホール、円山公園近くにあるKCS円山シティホール、そして中央区の外れに広大な駐車場を持つ葬祭本部のあるKCS札幌会館、その市内三つの館長をしている篠原弘道のことだ。篠原はKCSの設立当時からの中心メンバーで、年はまだ四十半ばだが、若者の面倒を良く見ているので、仲間内からは親しみを込めて[オヤジさん]と呼ばれている。
予定が立たない葬儀と違って、匠の仕事は予約制だ。今回も、公園で嫌な気配がするとの町内会からの依頼で出かけていた。仕事が終わった報告をする前に次の仕事の話がくることは原則的にないはずだ。
葬儀は予定が立たないから、重なる時は一日に十もの依頼が入る。葬祭部員は十名だが、昼夜交代で詰めているので実働出来るのは八名。それに葬儀に入ると丸二日かかる。
昔は葬儀の手配と見積もりだけで、あとは当番の営業代理店に任せて、すぐに次に控えている葬儀の依頼主の元へ走るなんて会社もあったようだ。
しかし、人の死を扱う以上、厳粛に対応せよとの北原社長の命で、KCSでは遺体の迎えから、火葬場から戻ってきた後の法要までを一貫して一人が担当している。
が、現場としては会員である顧客からの依頼を無下に断るわけにも行かず、どうしても手が足りない時は、匠が呼び戻されることがあった。
当然、表の仕事をさせられるのだと思って帰ってきた匠だが、葬儀が立て込んでいる様子はなく、呼び戻した当人は呑気にデビューもしてないアイドルの話をしている。しかも、館長が自分を呼び戻したという。
「ああ、もう十分くらいで現れるだろう。だからさ、匠ちゃんを退屈させないようにしてるんだろう」
どうやら写真を見せたいのは中山の方らしい。無駄口を叩きながらも、事務用のパソコンからネットに繋ぎそのホームページを開こうとしている。
何やら如何わしげな広告のあるページが、厳粛なはずの葬祭部平岸事務室のパソコン画面に浮かび上がる。
「ネットじゃかなり名の知れたアイドルオタクのホームページさ。アダルト広告はまあご愛嬌だな。そういや、こないだススキノで匠ちゃんを見かけだぜ。しっかし相変わらずロリな好みだな。しょんべんくさい小娘なんか抱いて面白いかな」
匠は顔色一つ変えず、女は妖艶な年増に限ると、これまたコアな好みを豪語する中山を視線だけで促した。
「たく、可愛げがないねえ。それだけの顔してりゃ、余計な金使わずとも落とす女にゃ事欠かないだろうに、勿体ない」
そう言いながらも、中山の右手はマウスをクリックし続けている。
やがて画面が切り替わり、年端の行かない子供が見ても、まず問題ない程度の画像が映し出された。市内の有名中学の制服を着た少女の上半身のグラビアだ。
ショートカットの少女の横顔。表情までははっきりしないが、何割か白人の血が混じったような白い肌をしている。S.T.というイニシャルがその下に入っている。
「元[リリック]の竹本由之の姪、竹本偲か。まあ、モノホンかどうかはわからんけどね。さて本命はこの次だ」
中山が画面をクリックすると、同じ制服を身に纏ったセミロングの髪の少女が現れた。同じようにR.K.というイニシャルがテロップで入っている。
隠し撮りしたようで、ピントが合っていないが、あどけない表情に匠は見覚えがあった。
「まあ、どうせ偽者だろうけどな。でも可愛い子じゃないか」
そう告げた中山が、匠を振り返って驚く。
「興味なさそうな顔してたわりにはこうだもんな、匠ちゃん、あんた本当にロリコンだったの?」
つい中山がつい軽口を叩いてしまいたくなるほどに、匠は身じろぎもせずに、画面を見つめていた。
――それは、西野匠が先程夕暮れの公園で見かけたあの少女だった。